従業員が会社に損害を与えて飛んだ!賠償を求めて良い?追跡するには?対処法を解説
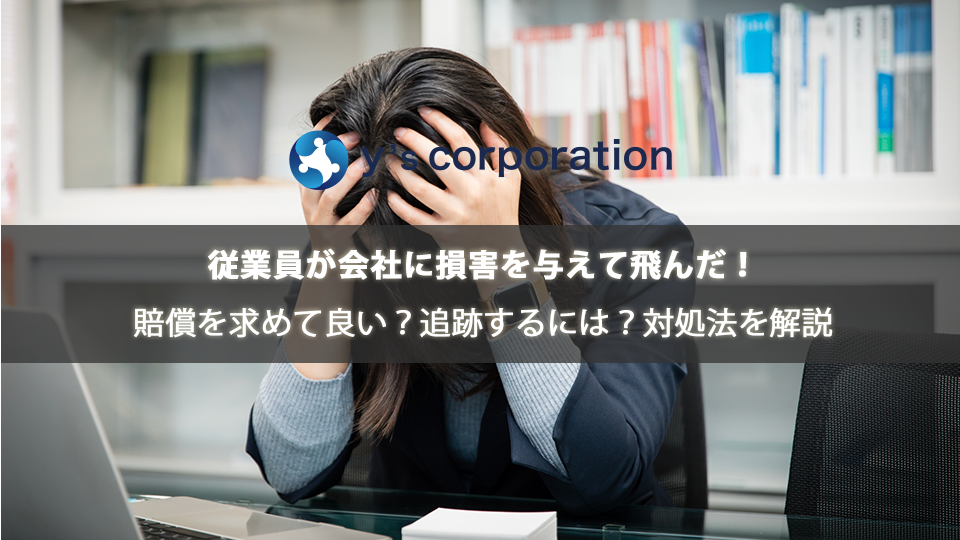
【記事更新 】
2025/05/27
会社に損害を与えた従業員が忽然と姿を消した…そんな事態、経営者にとっては冷や汗どころじゃ済まないですよね。従業員による損害が発生した場合どのように対処すれば良いのか、法的、実務的な側面から解説します。損害で資金繰りがままならないときの対応策として、ファクタリングについても解説します。
従業員が会社に損害を与えて飛んだ(突然退職した)場合の初動対応
従業員が損害を与えて突然いなくなってしまった場合、後の請求や法的措置のためにも初動が肝心です。
事実関係の迅速な確認と証拠保全
まず詳細な事実関係の把握に努め、証拠を確保しましょう。
証拠がなければ賠償請求や法的手続きが進められないため、関連書類やデータ、監視カメラ映像などを速やかに確認・保存してください。
実際に発生した損害と従業員の行為との因果関係を確認し、具体的な損害額を算定します。無断欠勤や横領などの場合は、会社側の管理体制や業務マニュアルの有無についても確認すべきです。
社内外への適切な情報共有と被害拡大防止策
被害が取引先や顧客にも影響する場合、速やかに関係者へ状況説明を行わなければなりません。風評被害を防ぐためにも、適切な情報開示が重要になってきます。
また、これ以上の被害拡大を防ぐため、該当従業員がアクセスしていたシステムや設備の権限を即時停止し、情報漏洩や追加損害を防ぐ措置も講じましょう。社内では再発防止のための原因分析と、就業規則や業務フローの見直しも欠かせません。
専門家への相談と今後の方針決定
損害賠償請求の可否や手続きの妥当性については、企業法務に強い弁護士への相談がおすすめです。現状考えうる法的リスク、請求可能な範囲を速やかに把握できます。
損害保険の適用範囲や今後のリスク管理体制の強化についても、専門家の意見を求めるとよいでしょう。対応のブレは信用低下につながるため、初動対応の段階で経営層や人事・総務部門と連携し、会社の方針を定めておきましょう。
従業員に損害賠償を求める際の法的ポイント
従業員に対する損害賠償請求は、法的に様々な制約があります。どのような場合に賠償請求が認められるのか、請求額はどの程度になるのか、法的なポイントを理解しておきましょう。
損害賠償請求が認められるケース
従業員の故意や重過失による損害発生時のみ、会社は損害賠償請求が可能です。単なるミスや軽過失では請求が認められにくいため、従業員の責任の程度を慎重に判断しなくてはいけません。
不法行為や債務不履行が明確な場合、民法709条や415条に基づき損害賠償責任が発生します。民法上の責任が明確に認められる状況でなければ、賠償請求は進めにくいです。
第三者に損害が生じ、会社が賠償した場合は、会社から従業員への求償権が発生することもあります。もし取引先や顧客への賠償金を支払ったのであれば、原因となった従業員へ請求できる可能性があります。
賠償請求額の制限と裁判例
従業員への損害賠償請求は、信義則や損害の公平な分担という観点から、全額請求が認められるケースは稀です。
多くの裁判例では減額されており、賠償額が10分の1、2分の1、4分の1に減額された例も。全額認められるのは、故意や重大な背任行為があった場合に限られるでしょう。
会社側の管理体制や過重労働、指導の有無も賠償額の判断材料です。状況次第では、従業員だけでなく会社側にも責任が問われることもあります。
【NG対応】損害賠償請求における注意点
給与から損害賠償額を天引きすることは労働基準法違反です。従業員の同意があっても裁判で認められるハードルは高いため、安易な給与控除は避けましょう。
仮に就業規則で賠償額を定めていても、労働基準法16条に反するため無効となります。損害賠償額の予定条項は、労働条件として認められていないのです。
また、損害賠償請求の前提として、損害発生の証拠や因果関係の立証が必要です。立証が十分でない場合は請求自体が認められないこともあるので、証拠収集は慎重に行いましょう。
従業員の行方を追跡するための実務的手段
損害賠償請求を行うためには、まず従業員の所在を特定しなくてはいけません。ここでは、突然退職して行方不明になった従業員を追跡する方法についてご説明します。
退職後の連絡手段と情報収集
退職時に提出された連絡先や身元保証人情報をもとに、まずは本人や身元保証人へ連絡してみましょう。
退職後、早いタイミングであれば住民票の移動や社会保険の資格喪失届など、公的情報を活用して所在を特定することも可能です。転居先の情報が得られれば、新しい住所宛てに連絡を取ることができます。
ただし、従業員が意図的に連絡を絶っている場合、弁護士を通じて内容証明郵便で請求書を送付する方法もあります。弁護士名での通知は心理的プレッシャーになることもあり、効果的です。
法的手続きによる所在調査
損害賠償請求訴訟を提起する場合、裁判所を通じて住民票の取得や調査嘱託を利用できます。調査嘱託とは、審理に必要な情報を裁判所を通じ、官公署やその他の団体に依頼する手続きです。
また、訴訟提起前でも、弁護士であれば職務上請求にて住民票を取得することが認められています。
身元保証人がいる場合、保証人に対しても損害賠償請求が可能ですが、保証契約の効果的期限や内容に注意が必要です。保証期間が経過している場合や保証範囲に該当しない場合は請求できないこともあります。
追跡が難しい場合の対応策
従業員の所在が不明で請求が進まない場合、訴訟や強制執行の実効性も低下するため、損害の回収が現実的でなくなることもあります。追跡調査が長期間に渡るようであれば、そのコストと回収できる可能性を天秤にかけなくてはいけません。
最終的に損失回収が難しい場合は、損害保険の適用や資金繰りが必要になってきます。損害を会社の損失として処理し、事業継続のための資金確保を優先することも時には必要です。
会社の損失補填を目的としたファクタリングの活用法
従業員による損害で資金繰りが悪化した場合、資金調達の手段としてはファクタリングがうってつけです。ここではその仕組みについて、詳しく解説していきます。
ファクタリングの基本的な仕組み
ファクタリングは、すぐには現金化ができない売掛債権をファクタリング会社に売却し、即座に資金を手にすることです。借入とは異なり、バランスシートに負債が計上されないというメリットもあります。
従業員の不祥事で資金繰りが悪化しても、売掛債権を現金化することで事業継続資金を確保できます。通常、入金まで2~3週間かかる売掛債権であっても、即日~数日で受け取ることが可能です。
2社間ファクタリングなら、取引先に知られずに資金を調達できます。資金繰りに困っているのでは?と勘繰られる心配もありません。
ファクタリング利用時の注意点
一方で、ファクタリング手数料は金融機関の融資より高い傾向があります。利用を検討する際は、コストと緊急度を比較検討することが大切です。
また、売掛債権の信用力や取引先の支払能力が審査対象となるため、すべての債権がファクタリングに適するわけではありません。取引先の信用度が低い場合、審査が通らなかったり手数料が高くなったりする可能性があります。
さらに、昨今はファクタリング会社を騙った悪質業者も増えてきているため、リスクを避けるためにも複数社から見積もりを取りましょう。
ファクタリング以外の損失補填策
損害保険の活用や、経営安定資金を利用するという手もあります。従業員による不正や横領などに対応する保険商品もあるため、加入している保険の内容を確認しましょう。
ただし、経営者保証や個人資産の持ち出しはリスクが高いです。会社の存続を優先するあまり、個人の資産まで投入するのは本末転倒と言えるでしょう。
今後のリスク管理体制強化のため、就業規則や内部統制の見直しも同時に進めることが望ましいです。再発防止策を講じることで、会社の信用回復にもつながります。
ファクタリングは、緊急時の資金調達手段にぴったりです。売掛金を現金化することで、急な資金調達にも対応することができるでしょう。
当社では、従業員の不祥事や突然の退職による資金繰り悪化にお悩みの経営者様からのご相談も、随時受け付けています。一人で悩まず、まずはお気軽にご相談ください。豊富な経験を持つ担当者が、最適な解決策をご提案させていただきます。







